みなさんこんにちは ! 管理人のありーなです
「ポータブル電源は欲しいけど、高いお金を出してまで本当に必要だろうか?」
そう考えている方もいらっしゃるのではないでしょうか?
今回の記事では、ポータブル電源の大きなメリットの一つ、「停電時に普段使いの家電がそのまま使える」という点に焦点を当てて深掘りしていきます。
災害による停電時という非常事態でも、使い慣れた家電が使えることは、私たちにとって大きな安心感につながります。
コンセントを差し替えるだけで使える手軽さも魅力です。
防災グッズとポータブル電源で使える家電を比較すると、ポータブル電源のありがたみがよくわかります。
被災時の情報収集、体温維持・管理、明るさ確保、調理など、停電時の具体的な状況と照らし合わせながらご紹介します。
また、いざという時にポータブル電源を焦らずすぐに使うための注意点もご紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。

ポータブル電源は、普段の生活の利便性を災害時にも提供し、「いつも通り」に近い状態を維持する上で、非常に心強い存在です。被災時だからこそ、慣れた家電が使えることが、私たちの精神的な負担を軽減し、前向きな気持ちにつながるのではないでしょうか
停電時、いつもの家電が使えるのが、ポータブル電源のメリットの一つ
当たり前のことかもしれませんが、ポータブル電源の大きな利点の一つは、普段使い慣れている家電製品を、災害による停電時でもそのまま使えるという点です。
懐中電灯やカセットコンロといった防災グッズも重要ですが、普段使っている家電は操作に慣れており、いざという時に戸惑うことなく使える安心感があります。
ポータブル電源があれば、複雑な操作は不要で、コンセントを差し替えるだけで、普段のように気軽に使えます。



災害への備えとして、懐中電灯やカセットコンロ、ラジオなどを準備している家庭もありますが、その割合は決して高くありません。さらに、これらの防災グッズを用意していても、すべてが揃っているとは限りません。また、いざ停電が発生した際に、すぐに取り出して使える場所に保管されているとも限りません
【災害への備えに関するアンケート調査】
2024年11月に、こくみん共済 coop〈全労済〉が全国の20~69歳 500人に対して「防災・災害に関する全国都道府県別意識調査」を実施しました。
その結果、災害が発生した際の防災対策について、「平時に備えることができている」とした人はわずか27.8%(3割未満)でした。「備えができている」と回答した人が、具体的にどのような対策を行っているかの内訳は以下の通りです
| 水や食料 の備蓄 | トイレの 備え | 歯磨きや体を清潔にする衛生用品備え | 薬(応急処置用品、持病等の薬等)の備え | カセットコンロやボンベの備え | 懐中電灯やLEDランタンなどの備え | ラジオの備え | 蓄電池や充電器などの備え | |
| 20代 | 28.1% | 14.6% | 24.6% | 30.3% | 20.8% | 38.4% | 17.7% | 25.1% |
| 30代 | 32.9% | 18.1% | 28.2% | 30.9% | 30.3% | 46.4% | 22.8% | 28.6% |
| 40代 | 33.9% | 18.8% | 28.2% | 30.0% | 35.0% | 52.7% | 29.4% | 32.3% |
| 50代 | 38.1% | 19.6% | 32.1% | 34.2% | 38.6% | 56.9% | 37.5% | 34.9% |
| 60代 | 43.3% | 21.6% | 34.4% | 37.8% | 47.1% | 63.8% | 49.4% | 40.7% |
| 平均(参考) | 35.3% | 18.5% | 29.5% | 32.6% | 34.4% | 51.6% | 31.4% | 32.3% |
※ こくみん共済 coop〈全労済〉「防災・災害に関する全国都道府県別意識調査」調査結果の表の一部を引用し、筆者が各年代の回答数を100名として単純平均を算出して追記したものです(実際の有効回答数は4,935だが、年代別の内訳不明なため)
この調査では、「万が一、在宅時に災害が発生したときに備え、あなたは以下の防災対策ができていますか?」と質問したところ、最も多かった回答は「懐中電灯やLEDランタンなどの備え(51.6%)」でした。一方で、カセットコンロやラジオ、蓄電池などの回答は3割台にとどまる結果となりました



これからさまざまな種類の防災グッズを揃えるなら、思い切ってポータブル電源とソーラーパネルを買ってしまう方が良いかもしれません。次の章では、ポータブル電源と防災グッズを比較して紹介します
目的別、ポータブル電源で使える家電と防災グッズ
ポータブル電源があった場合に使える家電と、それと同じ目的を防災グッズで果たそうとした場合を比較してみました。
目的に分けて、その目的を果たすために使えるものを例示します。
被災時の情報収集に使えるもの


ポータブル電源があれば、停電時でも普段利用しているテレビやパソコン、ルーターなどが使用でき、情報収集の手段を確保できます。
また、スマートフォンやタブレットも複数回充電可能です。
一方、ポータブル電源がない場合は、防災用のラジオや、スマホ充電用のモバイルバッテリーなどを別途備える必要がありますが、情報量や利便性は普段使いの家電に劣ります。
被災時の体温維持・体温管理に使えるもの


ポータブル電源があれば、夏場の扇風機や冬場の電気毛布、電気ヒーターなど、普段使っている冷暖房器具を活用して、被災時でも比較的快適な体温を維持できます。
特に、小さなお子さんや高齢者のいる家庭では重要です。
一方、ポータブル電源がない場合は、うちわや使い捨てカイロ、寝袋や毛布などが主な備えとなりますが、温度調整の範囲や快適性は大きく劣ります。
被災時の明るさ確保に使えるもの


ポータブル電源があれば、普段使っているスタンドライトやデスクライトなどをそのまま利用でき、広範囲を明るく照らすことが可能です。
これにより、夜間の移動や作業の安全性が高まります。
一方、ポータブル電源がない場合は、ろうそくや電池式の懐中電灯などが主な選択肢となりますが、ろうそくは火災の危険性があり、電池式ライトは明るさや持続性に限界があります。
電池を使う懐中電灯やライトを使う場合も、充電式乾電池を使えば、ポータブル電源で繰り返し充電しながら使えます。
被災時の調理に使えるもの


ポータブル電源があれば、電子ケトルでお湯を沸かしたり、炊飯器で温かいご飯を炊いたり、電気鍋やホットプレートで簡単な調理をしたりすることができます。
電子レンジが使える機種もあり、調理の幅が広がります。
一方、ポータブル電源がない場合の調理は、カセットコンロや固形燃料ストーブなどが考えられますが、燃料の確保や換気、火の扱いに注意が必要です。
被災時の保冷・保温に使えるもの


ポータブル電源があれば、一時的に冷蔵庫や冷凍庫を動かすことができ、食料品の腐敗を遅らせることができます。
特に、夏場の長期停電時には非常に重要です。
一方、ポータブル電源がない場合の保冷手段としては、クーラーボックスや保冷バッグなどが考えられますが、保冷力には限界があり、長期間の保存には適していません。
ポータブル電源をいざという時、焦らずすぐに使えるために
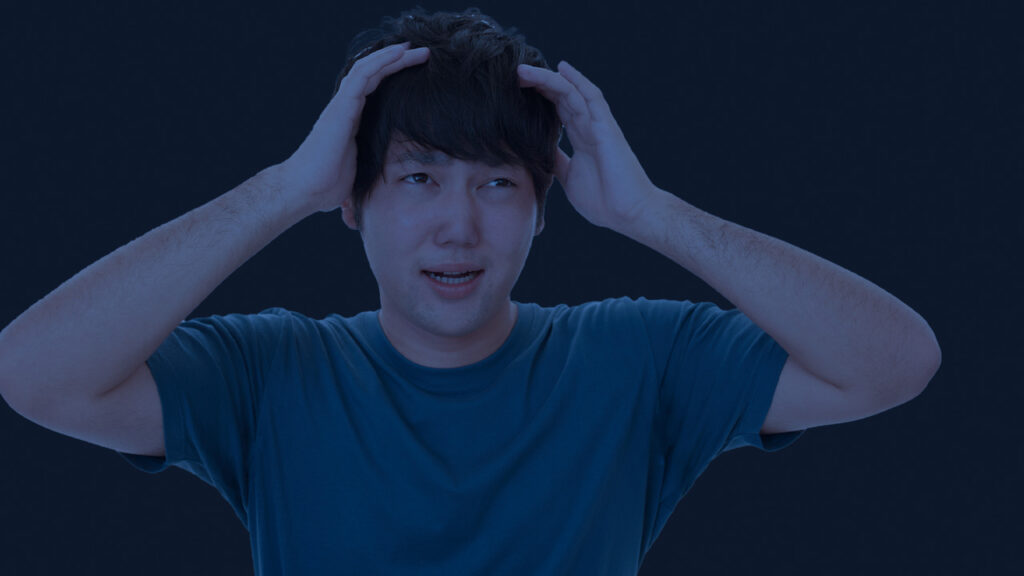
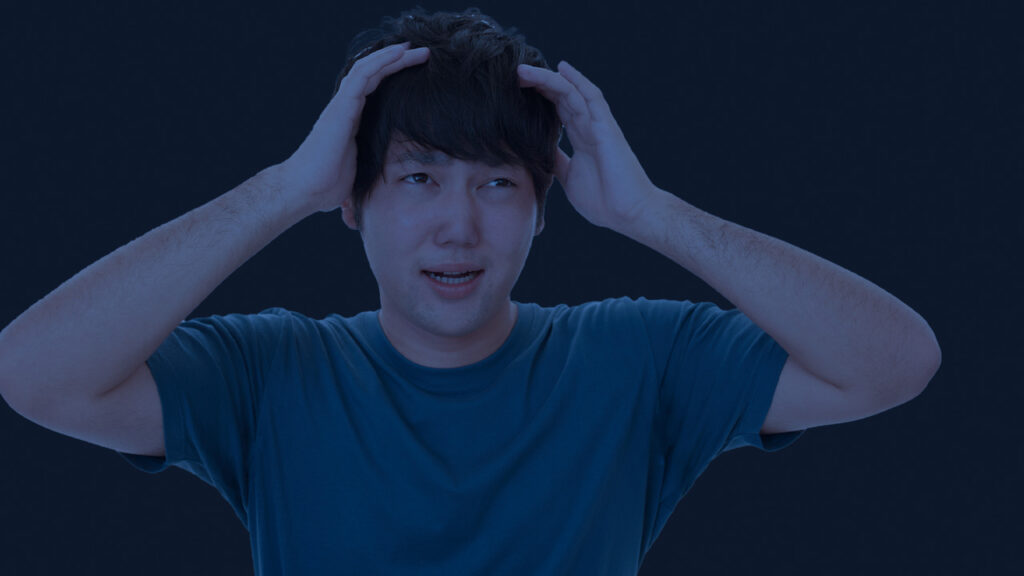
ポータブル電源の大きな利点の一つが、停電時でも家電製品をすぐに使えることですが、そのメリットを生かすためには、ポータブル電源がすぐに使える状態になっていなければなりません。
ポータブル電源をすぐに役立てられるように、気を付けておくべきことを紹介します。
日常的な充電習慣:バッテリー残量を常にキープしておく
ポータブル電源が、いざという時にバッテリー切れで使用できないという事態を避けるため、日常的な充電習慣が重要です。
日常的に使わないのであれば、月に一度など定期的な頻度で充電を行い、常に一定以上の残量を保つように心がけましょう。
普段から使用している家電製品をたまにポータブル電源で動かしてみるのも、動作確認と充電の習慣化に繋がります。
満充電にして保管することが基本ですが、長期間保管する場合は過充電を避けるため、メーカー推奨の充電量を守りましょう。
置き場所を決める:取り出しやすく安全な場所へ
緊急時にポータブル電源をすぐに取り出せるよう、置き場所を決めておくことも大切です。
もし夜間に停電が起きれば、室内は真っ暗で気持ちも焦ります。
ポータブル電源の置き場所が決まっていれば、焦ることなくポータブル電源をすぐ使うことができます。
定期的な動作確認:問題がないかをチェック
いざという時に確実に動作するように、ポータブル電源を定期的に動作確認することが重要です。
簡単な家電製品を接続して、正常に給電できるかを確認しましょう。
また、バッテリーの充電・放電サイクルも確認し、極端に劣化していないかをチェックすることも大切です。
もし異常が見られた場合は、早めにメーカーに問い合わせるなどの対応を取りましょう。
ソーラーパネルとの連携:電気を自給自足できる体制づくり
いざという時にポータブル電源をすぐに使うためには、常に充電されている状態にしておく必要がありますが、電気を使えばバッテリーの残量は減っていくもの。
そこで重要になるのがソーラーパネルとの連携です。
停電時でも、ソーラーパネルがあれば太陽光で発電し、ポータブル電源に電気を補充できます。
実際に電気が必要になったときにスムーズに充電できるよう、ソーラーパネルの使い方は事前にしっかり把握しておきましょう。
実際に何度かソーラー充電を試して、その手順や充電時間を体験しておくことも大切です。こ
れにより、いざという時でも慌てずに、電気を自給自足できる体制が整います。
周辺機器の用意:ケーブル類をすぐに使える状態に
停電時にポータブル電源を使う際、使いたい家電製品が電源のすぐ近くにあるとは限りません。
例えば、照明、パソコン、電子レンジなどを同時に使いたい場合、すべての家電製品をポータブル電源のそばに移動させるのは難しいかもしれません。
そんな時に活躍するのが延長コードです。
ポータブル電源の近くに延長コードを備えておけば、少し離れた場所にある家電製品でも、延長コードを介してポータブル電源から給電できます。
実際に停電が起きた場合を想定して、使用したい家電製品を使う際に何か不都合がないか、他に何か必要なものはないかを事前に確認しておきましょう。
これにより、いざという時にスムーズに電気が使えるようになります。
まとめ:災害時、いつもの家電が使えるポータブル電源は、やはり便利
ポータブル電源の最大のメリットは、停電時でも普段使い慣れた家電をそのまま使える点です。
懐中電灯やカセットコンロなどの防災グッズの備えももちろん重要ですが、操作に慣れた家電は安心感があります。
コンセントを差し替えるだけで使える手軽さも魅力です。
万が一の事態に備え、ポータブル電源を常に充電し、置き場所を決め、定期的に動作確認を行いましょう。
ソーラーパネルや延長コードなども活用し、電気を自給自足できる体制を整えることが重要です。
\ 人気のポータブル電源を安く買うなら/



















コメント